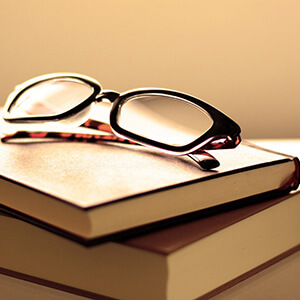はちみつの種類と違い。おいしいはちみつの選び方とは?

みなさん、はちみつはお好きですか? 料理やスイーツに使ったり、朝食のトーストやパンケーキ、ヨーグルトにかけたり・・・。メイン食材にはならなくても、味や香りのアクセントとして、そして何よりそのまろやかな甘みを求めて、はちみつを使う方は多いことでしょう。栄養価も高く、「最も古いスーパーフード」とも呼ばれるはちみつ。
この記事では、はちみつの栄養価と、どんな種類があるのか、上手な選び方をご紹介します。
- はちみつはビタミンやミネラルが豊富
- 1種類の花の蜜を単花蜜、複数の花の蜜は百花蜜
- 日本人好みはレンゲとアカシアのはちみつ
- 選んで買うなら“単花蜜”
この記事でわかること
はちみつの効能あれこれ
優れた栄養成分
はちみつは、良質なビタミンやミネラル、アミノ酸、さまざまな酵素といった栄養素が豊富に含まれています。歴史も大変古く、スペインでは石器時代の痕跡が残る洞窟に、はちみつを集める女性の姿が描かれた岩絵があります。
日本では飛鳥時代に、養蜂を試みたが上手くいかなかった、という記録があり、奈良時代には朝廷への貢ぎ物として名前が挙がります。江戸時代に入ると養蜂が本格的に行われるようになり、明治時代には西洋ミツバチが輸入されて近代化します。

はちみつの約80%は糖分で、残りの約20%が水分です。80%を占めるブドウ糖と果糖は、疲労回復に有効とされる単糖類です。一般に、摂取された糖類は単糖類(ブドウ糖や果糖)に分解されて体内に吸収されますが、はちみつに含まれる糖類はミツバチが花の蜜を体内の酵素で分解したものなので、すでにブドウ糖と果糖の形に分解されています。そのため、消化吸収に手間がかからず、すぐに体のエネルギー源になります。
さらに、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素など体にうれしい栄養成分が150種類以上もバランスよく含まれており(一説には300種類とも言われます)、「パーフェクトフード」と呼ばれるほど。腸内環境を整えるグルコン酸やオリゴ糖、抗酸化・抗炎症作用でメタボリックシンドロームを軽減するポリフェノールも含まれています。
殺菌作用と保存性
はちみつの代表的な効能として、今ではあまり意識することはありませんが、強い殺菌作用があります。その殺菌作用は、古くは傷の治療などにも使われてきました。はちみつは80%という高い糖度を保っているため、細菌が繁殖できません。ブドウ糖由来の過酸化水素(別名オキシドール)が含まれていることも、殺菌力の高さの所以です。グルコースオキシターゼという酵素が含まれていて、水が加わるとさらに過酸化水素が発生します。そのため強い殺菌作用を発揮します。
また、糖度が高いことも殺菌・抗菌作用の助けになります。浸透圧現象によって、細菌の水分を奪ってしまうので、細菌が活動できません。このことから、はちみつは腐りにくいと言われています。ただし、殺菌作用があってもボツリヌス菌の芽胞だけは生きているので、1歳未満の赤ちゃんには与えないようにしましょう。

はちみつを開封すると冷蔵庫に入れたほうがいいか悩むところですが、冷蔵庫に入れると糖分が結晶化してしまいます。はちみつは15度くらいになると結晶化が始まってしまうので、常温で直射日光が当たらない、涼しい場所で保存しましょう。湿気の多い場所を避けて食器棚や戸棚など、できるだけ湿気が少なく風通しの良い場所に置くのがおすすめです。
天然のはちみつであれば賞味期限を過ぎても腐ることはありませんが、口につけたスプーンや指を入れることで雑菌が繁殖する可能性はあります。清潔なスプーンを使うように心がけましょう。
単花蜜と百花蜜
ミツバチを育て、ミツバチが蜜を集めてきた後に、巣箱から巣板を取り出し、遠心分離機にかけて蜜を取り出したものがはちみつです。何も加えず、ミツバチが集めてきたものだけ・・・正真正銘の自然食品ですね。
ミツバチが集めてくる蜜のもととなる花(蜜源)により、はちみつの色や香り、味が異なり、はちみつの種類が決まります。まずは大きく単花蜜と百花蜜の2種に分けられます。

単花蜜
採蜜量の多い西洋ミツバチが、1種類の花から集中して集めた蜜です。採蜜した時期や地域によって味や香りは微妙に異なりますが、花蜜ごとにおおむね安定した味わいとなります。花ごとに風味が異なるので、使い方に合わせたり、自分の好みを探したりしてみるのもいいですね。
百花蜜
複数種類の花の蜜が混ざったものです。日本ミツバチは採蜜量が少ないため、基本的には1年に1回しか巣からしぼることができません。そのため、日本ミツバチが集めたはちみつはすべて百花蜜になります。また西洋ミツバチも、採蜜量が少ない場合には他の花から採蜜した蜜も混じってしまい、百花蜜となる場合があります。
単花蜜のいろいろ
味や香りなど、それぞれの花の風味をそのまま楽しめる単花蜜。色が淡いものは香りも柔らかく、クセも強くない傾向にあります。色が濃くなるにつれて香りや味が濃厚となり、それに比例してクセが強くなっていくと言われています。
| レンゲ(マメ科) | |
|---|---|
| 主な産地 | 中国、日本 |
| 花の時期 | 春 |
| 色 | 淡い黄色 |
| 味・香り | ほのかにフローラルな香り まろやかな口当たりでクセがない 上品な甘さが日本人に人気 国産の単花蜜は高級品 |
| 料理 | トースト、ヨーグルト、肉料理、魚料理 |
| アカシア(マメ科) | |
|---|---|
| 主な産地 | 日本、中国、ハンガリー |
| 花の時期 | 初夏 |
| 色 | 薄い黄色 |
| 味・香り | フローラルな優しい香り 上品な風味で結晶化しにくいのが特長 くせのない穏やかな甘さ 日本人好み |
| 料理 | トースト、ミルク、そのまま |
| クローバー(マメ科) | |
|---|---|
| 主な産地 | カナダ |
| 花の時期 | 初夏~夏 |
| 色 | 淡い黄色 |
| 味・香り | 上品でほのかな香り 後味すっきり 天然のはちみつポリフェノールが豊富 グルコン酸が豊富 |
| 料理 | ヨーグルト、フルーツ、紅茶、シリアル |
| みかん(みかん科) | |
|---|---|
| 主な産地 | 日本 |
| 花の時期 | 初夏 |
| 色 | オレンジがかった色 |
| 味・香り | 柑橘類独特のさわやかな香り 粘性が強く、すっきりとした甘み 後味もさわやか |
| 料理 | レモネード、ヨーグルト、紅茶、トースト |
| ラベンダー(シソ科) | |
|---|---|
| 主な産地 | スペイン、日本 |
| 花の時期 | 初夏 |
| 色 | 琥珀色 |
| 味・香り | ハーブ特有の心地良い香り 甘さは強めだが後味はさわやか 香りを楽しむのがおすすめ |
| 料理 | 紅茶、トースト、ヨーグルト、アイスクリーム |
| そば(タデ科) | |
|---|---|
| 主な産地 | 中国、日本 |
| 花の時期 | 夏~秋 |
| 色 | 黒砂糖のような濃色 |
| 味・香り | 力強い香り 黒蜜のようなコクと独特の風味 やや苦みがある 鉄やミネラルを多く含む |
| 料理 | わらびもち、ところてん、ガレット、味の濃い肉料理 |
| くり(ブナ科) | |
|---|---|
| 主な産地 | 日本 |
| 花の時期 | 初夏 |
| 色 | 茶褐色 |
| 味・香り | くり独特の香り 渋皮のようなほろ苦さがある 鉄分が他のはちみつに比べて特に多い ビタミン量も豊富 |
| 料理 | 濃い目の料理、チーズ、モンブラン |
| マヌカ(フトモモ科) | |
|---|---|
| 主な産地 | ニュージーランド |
| 花の時期 | 初夏 |
| 色 | オレンジに近い褐色 |
| 味・香り | ややスパイシーな香り クリーミーな食感でコクがある 濃厚で個性的な味わい |
| 料理 | 濃い目の料理、ソースの隠し味、トースト、コーヒー、紅茶 |
はちみつの選び方
種類が多く、どれを買おうか迷ってしまうことも多いはちみつ。おいしいはちみつに出会うために、以下のことを気に留めてみてください。

純粋はちみつを選ぶ
日本ではちみつの表記で流通しているものは、大きく分けると純粋はちみつ、精製はちみつ、加糖はちみつの3種類です。純粋はちみつは、一切加工されていない天然のはちみつ。精製はちみつは、はちみつから色や匂いを取り除いたものになります。加糖はちみつは、純粋はちみつに水飴などを加えたものです。
はちみつ本来の味や香りを楽しむなら、ラベルを確認して、ぜひ純粋はちみつを選んでください。もちろん、養蜂場や養蜂家が明記されているものであれば、より安心ですね。
花のイメージだけで選ばない
たとえば、そばの花は白くて可愛らしい花ですが、その見た目と裏腹に黒蜜のような色と濃厚で独特な香りと味があります。ネットなどで買って「思ったのと違う……」とならないように、最初はお店でちゃんと色を見て、できれば専門店で試食するといいかもしれません。

初めての単花蜜ならアカシアかレンゲを
単花蜜を買うのは初めてで何もわからない、そんな時はアカシアかレンゲをおすすめします。この2つはクセが少なく、日本人に好まれるタイプのはちみつです。
そこからちょっと冒険したいという方には、みかんやオレンジ、りんご、レモンなど果実系がおすすめ。果実系のはちみつは、たとえばみかんやオレンジならほのかな酸味があったり、リンゴはフルーティな味わいがあったりなど、その果実のイメージに通ずるものがあるので親しみやすいですよ。
はちみつはあまり熱を加えずに
はちみつは温度が低いほうが甘みをしっかり感じられる性質があります。高温のほうが甘みを感じやすい砂糖とは違いますね。はちみつを60度以上に加熱すると、栄養成分が損なわれるほか、香りや風味が飛んでしまったりすることも。ホットのコーヒーや紅茶にはちみつを加える場合は、少し冷ましてからにすると、風味も栄養も損なわずに楽しめます。